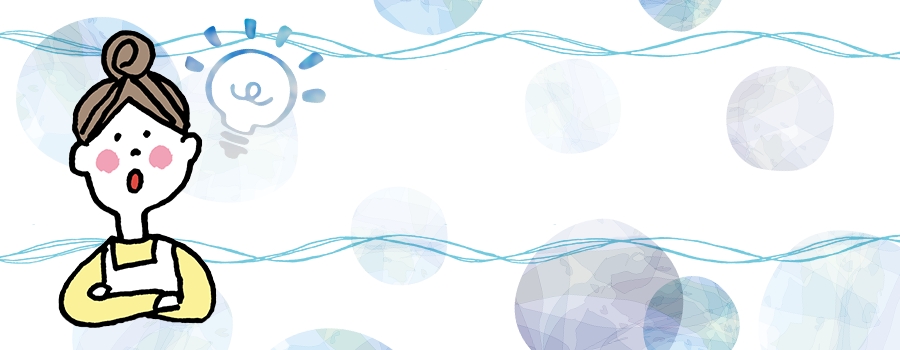
水道事業が民営化する背景には水道管の老朽化や収益減があります。
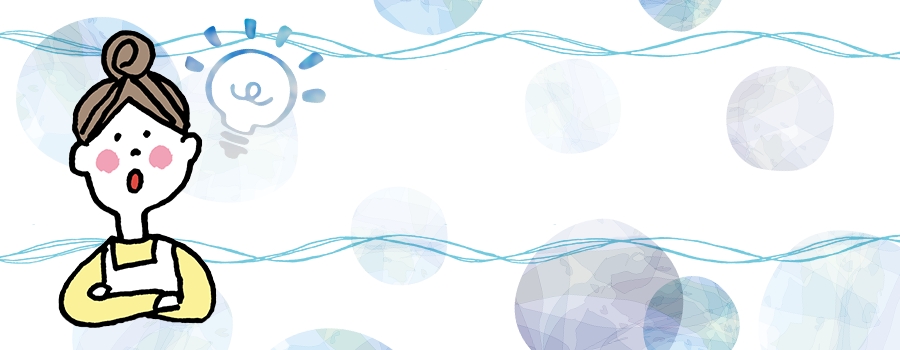
水道民営化で何が変化する?
水道民営化でどう変わる?
2018年7月5日に水道法の改正案が衆議院で可決された事をご存知ですか?
この可決案の中には今まで各市町村が運営していた水道事業を民営化する、という内容も含まれています。
公営だったものが民営化されたもの、というと一昔前だと現在のJRである国鉄や、新しいところだと郵政の民営化、というものがありましたよね。
さて、水道事業が民営化、というのはそもそもどういうことで、私たちの生活にどのような変化が起きるのでしょうか?
そもそも水道事業の民営化とは
 先も述べたように水道事業は今まで各市町村が運営する国の事業でしたが、民営化することによって「国と民間企業の共同事業」となるのです。これを「コンセッション方式」といいます。
先も述べたように水道事業は今まで各市町村が運営する国の事業でしたが、民営化することによって「国と民間企業の共同事業」となるのです。これを「コンセッション方式」といいます。
これは一体どういうことかと言うと、水道の所有権は公的機関、要するに国に残したまま、事業の運営を民間事業者が行う、ということです。
ではなぜこのような法律を作り水道事業を民営化する必要があったのでしょうか?
今まで水道事業の運営は自治体が行っていました。そのため水道管のメンテナンスなどは国が行っていたわけです。
しかし、水道の整備が進んだのは1970年代。
それから今現在まで約50年もの月日が経っています。
するとどういう現象が起こるかというと、「水道管の老朽化」が進んでいきます。
水道管の耐久年数は地上公営企業法施行規則で40年と定められています。
しかし、1970年代やそれ以前の水道管が全部更新されているのか、というとそういうわけでもありません。
2014年のときに行われた調査によると、耐用年数の40年を越えた水道管は12%ほどあり距離にして約80,000km、そのうち1年で交換できる長さは5,000kmほどしかなかったそうです。
このままの調子で交換していくと、30年後には50%以上の水道管が耐用年数を越えてしまいます。
耐久年数を越えた水道管をそのまま使用し続けると、水道管が破裂し、中がさびてしまいきれいな水が供給できなくなる恐れがあります。
また、水道管の交換には多額の費用がかかります。
その費用を今までどのように捻出していたかというと、国や自治体からの補助金と我々が納めた水道料金によりメンテナンスが行われていました。
国や自治体から出す費用と言うと、要するに税金から出しているわけです。
しかし、少子高齢化が進み、地方自治体は過疎化も進んでいっているため、様々な理由から水道管の交換・維持が難しくなっています。
これはよくニュースなどにもなりますよね。
水道料金が値上げされる可能性が高い
このような理由から水道事業の民営化が行われる事になりました。
皆が一番気になるのは「水道料金の値上げ」ですよね。
これに関しては値上げされる可能性が高い、といえるでしょう。
その理由、1つは老朽化した水道管の交換費用、1つは民間事業者なので「利益」を得られなければお話になりませんよね。
実際、水道事業が民営化された諸外国では水道料金が5倍近くになり、再度公益化された、という事例もあります。
どのくらい値上げされるのか、は人口比率や事業を請け負った事業者によるのでなんともいえません。